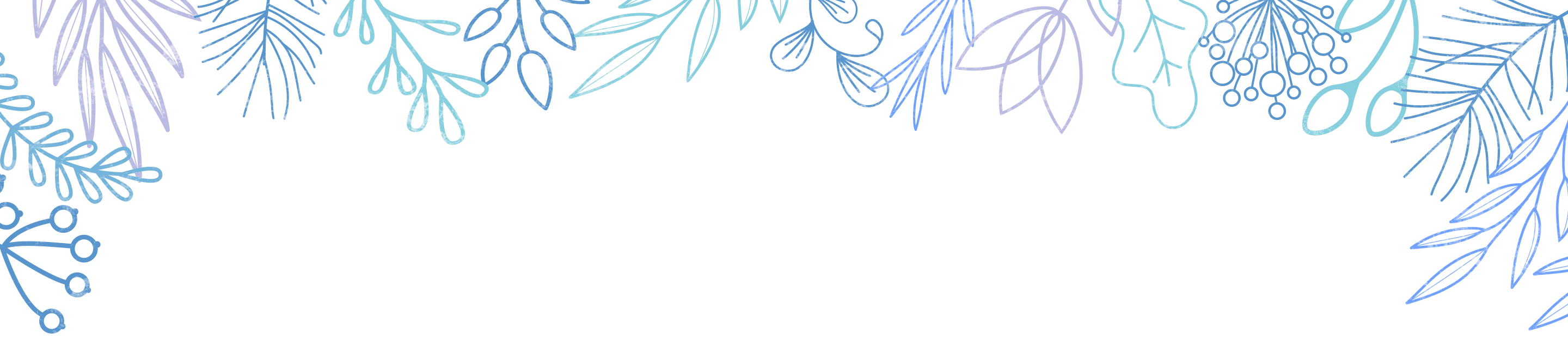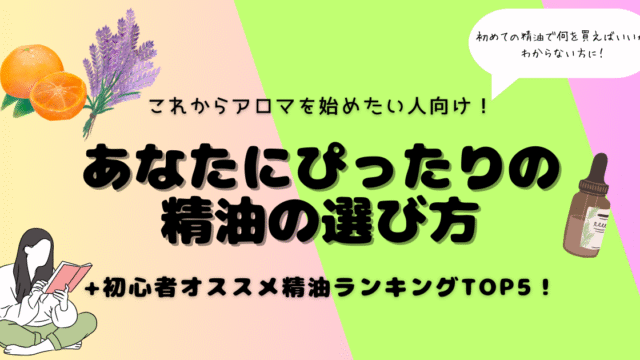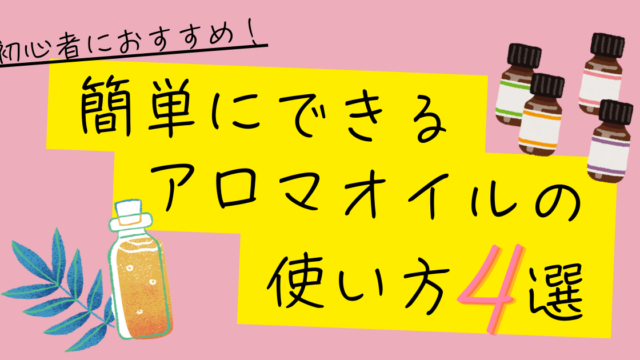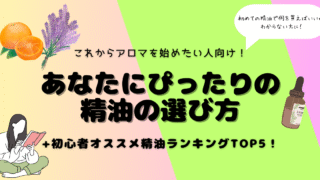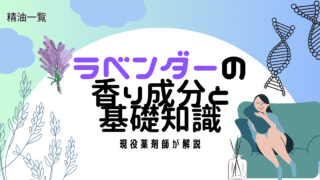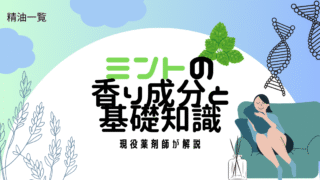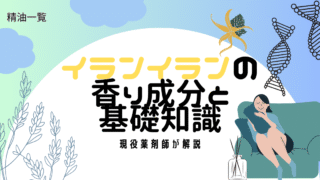子供の結膜炎、花粉症…医師にそんなことを言われて処方された目薬。使おうにも逃げるし嫌がって泣き出す子供たち。
「どうやって目薬を点せばいいの⁉」
そんな悩みを持つお母様へ、今回は4つの子供の点眼方法をお伝えいたします。
子供への点眼方法
太ももで頭を固定して目薬を点す
そこまで暴れない子向け。
- 子供を大の字に寝かせます。
- その上から大人が足を延ばして子供の上半身を固定するようにまたがります。
- 太ももで頭を挟みます。
- 下まぶたを引っ張って点眼液を垂らします。
目をつぶってもらって、下まぶたを引っ張って目薬を入れる
目薬を向けられるのが怖い子向け。
- 子供に目をつぶってもらいます。
- 下まぶたを引っ張って点眼液を垂らします。
目薬の先端を向けられるのが嫌なだけで、この方法で点眼できる子は意外と多いです。
寝ている間に点す
どうしても暴れてしまって点眼ができない子向け。
- 子供が寝ているのを確認します。
- 起こさないように下まぶたを引っ張ります。
- 点眼液を垂らします。
これが一番やりやすいです。でも、目薬を1日に何度も点す場合は毎回寝てもらうわけにもいかないので、タイミングが難しい方法です。
どうしても目の中に薬を入れられない場合は目頭に垂らす
寝てくれない時や、目薬を目の中に落とされるのが嫌な子向け。
- 目の周りを拭いて清潔にします。
- 子供に目をつぶってもらいます。
- 目頭あたりに目薬を垂らします。
- お子様に少し瞬きをしてもらうと目の中に薬が入っていきます。
- 最後に目のまりについた薬を拭きます。
この方法なら多少動いてしまっても目の中に薬が入って効果が期待できます。目の周り専用の洗浄綿もあります。
注意すること
泣いてしまうと涙と一緒に薬が出てしまう
嫌がっている子供にやっと目薬を点せた!でも泣いてしまうと涙と一緒にせっかく点した薬が流れ出てしまい、薬の効果が発揮できなくなってしまいます。
子供たちが怖がらずに目薬を使えるようになることが重要です。
目の周りについた薬はしっかりとふき取る
目の周りに薬が残ってしまうと、かゆみや炎症を引き起こす可能性があります。目の周り専用の洗浄綿も売っていますので、よかったら使ってみてください。
目薬の容器の先端を当てない
目薬の先端をまぶたやまつげに当ててしまうと、衛生上あまりよくありません。まぶたやまつげから汚れがついて菌が繁殖してしまうと、目薬が汚染されてしまいます。
目薬のまめ知識
「よく振って」と書いてある目薬
目の炎症を抑えてかゆみを抑えてくれるフルオロメトロンなどの容器には「よく振ってから使用してください」と書いてあります。このように書いてある目薬は懸濁性点眼液であることがほとんどです。
懸濁とは液体の中にとっても細かい薬の粉が分散している(散らばっている)状態のことです。放置すると下の方に細かい薬の粉が溜まってしまいます。なのでよく振らないとお薬がうまく出てこないです。
2種類以上の目薬が処方されたとき
まず、使う順番ですが、基本的にはサラサラ→ドロドロの順番で使用します。
サラサラには水溶性点眼液があります。ドロドロは懸濁性点眼液、ゲル化点眼液があり、上記の右に行くほどドロドロします。
ですので、使用する順番は水溶性→懸濁性→ゲルの順番です。同じ種類の性質をもつものであればどちらが先でも基本かまいません。
また、目薬を2種類以上使う場合は次を使うまで少し間隔をあけます。2種類以上の目薬を間隔をあけずに点したら、あふれ出てしまいます。目薬は目にとどまっている間が効果が出てている状態なので、目からあふれ出た薬は無駄になってしまいます。
サラサラを使った後は5分間隔をあけて次を使います。
ドロドロは目にとどまる時間が長いため、10分間隔をあけて次を点します。
眼軟膏と目薬が一緒に処方されたとき
眼軟膏はとても固く目にとどまりやすいので、一番最後に使います。硬い場合は手で少し温めると少しトロっとします。
眼軟膏は下まぶたに乗っけるように使います。使った後は目の前が白くぼんやりしますが、軟膏が溶けると視界も戻ります。
眼軟膏も目薬と同様に容器の先を肌につけないように使ってください。
まとめ
今回はお子様への目薬の点し方を4つご紹介いたしました。点眼に限らず、お子様へのお薬の服用は本当に大変だと思います。
お薬は今だけでなくこの後何度も使用する機会があります。その時お子様が嫌がらない、怖がらないで続けられる工夫がとても重要だと考えています。
他にもお薬服用に関する工夫はたくさんありますので、お困りの場合はぜひ薬剤師にご相談ください。
※お薬の説明は法律や研究によって内容が変わることがあります。正しい最新の情報をしっかりと確認してください。