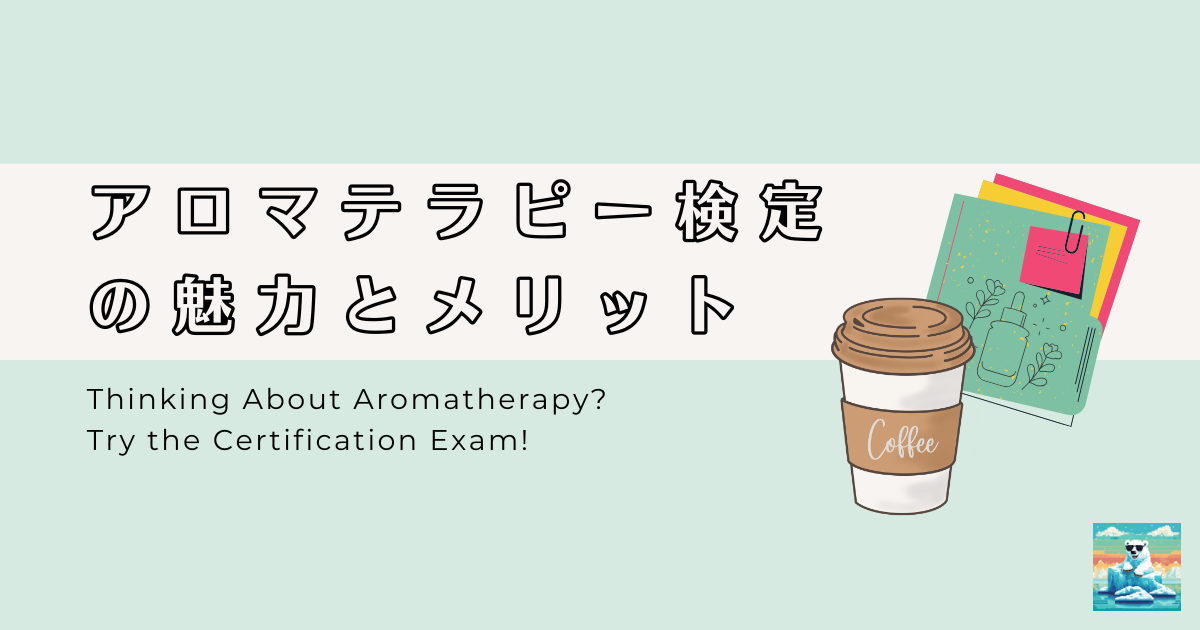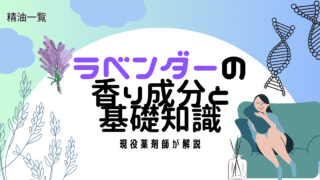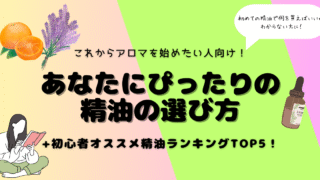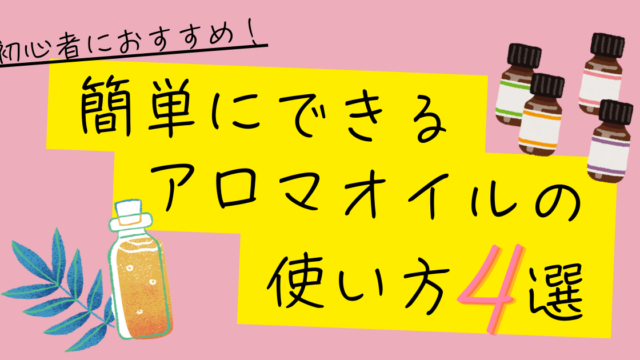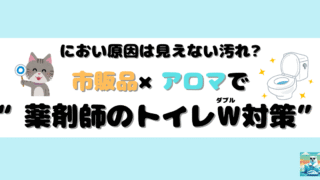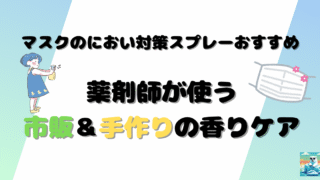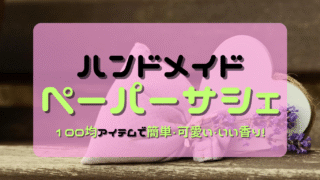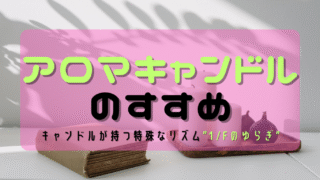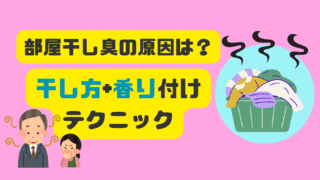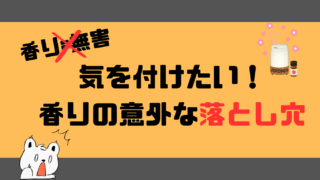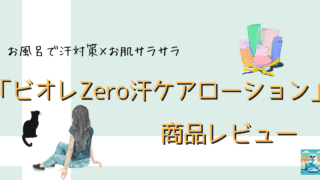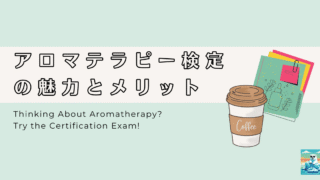アロマテラピー検定は、こんな人におすすめ!
・自分や家族の健康維持にアロマテラピーを活かしたい
・アロマテラピーを体系的に学びたい
・さらに上位の資格取得を目指したい
・今の仕事に香りの知識を活かしたい
(引用:日本アロマ環境協会[AEAJ]公式サイト)
アロマが好きで精油を使い始めたけれど、「もっと上手に活用できたらいいな」と感じたことはありませんか?
そんな方にぴったりなのが、アロマテラピー検定です。
この記事では、薬剤師のおシロが、
を、解説します。
香りの選び方や使い方、安全性の基本までを体系的に学べるこの検定は、アロマ初心者が一歩ステップアップするのにぴったり。
資格といっても堅苦しいものではなく、香りを楽しむための“学びの入口”として、多くの人に選ばれています。
アロマテラピー検定を受けたい方へ
👇公式テキスト&問題集はこちら!👇
アロマテラピー検定とは?
 画像引用:(公式)日本アロマ環境協会公式サイト
画像引用:(公式)日本アロマ環境協会公式サイトアロマテラピー検定は、公益社団法人 日本アロマ環境協会(AEAJ)が主催する、香りに関する正しい知識を学ぶための資格試験です。
精油の基礎知識や、安全に使うための注意点、生活への取り入れ方までを体系的に学べる内容で、アロマ初心者の方にも広く選ばれています。
検定は年に2回(5月・11月)に実施され、オンライン形式の自宅受験が可能。
受験資格に制限はなく、学生さんや主婦の方、美容・医療・福祉の現場で働く方など、“人に寄り添う仕事”をしている方々にも人気があります。
アロマ関連の資格は他にも複数ありますが、アロマテラピー検定は、
といった点から、「まずアロマを学び始めたい」という方に最適です。
香りを楽しむための知識としては、この検定で十分。
もし将来的に仕事や専門的な資格を目指す場合は、1級取得後に「アロマアドバイザー」や「アロマインストラクター」など、次のステップに進む道も用意されています。
1級と2級の違い【どっちを受ける?】
アロマテラピー検定には「2級」と「1級」があり、試験範囲や難易度、学べる内容にいくつか違いがあります。
| 項目 | 2級 | 1級 |
|---|---|---|
| 出題範囲 | アロマの基礎知識、安全性、使い方など | 2級範囲に加え、歴史、法律、体への影響などを含む |
| 精油の種類 | 11種 | 30種 |
| 試験の難易度 | 初心者向け(初学者向けの内容が中心) | 少し深い内容も含まれるが、独学でも合格可能 |
| 合格メリット | アロマを生活に取り入れる基本を学べる | 上位資格(アロマアドバイザーなど)取得へのステップに |
| 試験形式 | オンライン・自宅受験 | オンライン・自宅受験 |
どちらも受験資格に制限はなく、1級からの受験も可能です(2級→1級の順で受ける必要はありません)。
「まずアロマを学んでみたい」という方は2級からでもOK。
ただ、精油の種類が2級は11種・1級は30種と大きく異なるため、
本格的に学びたい・資格を活かしたい方は最初から1級を受けるのもおすすめです。
ちなみに私は最初から1級を受けましたが、公式テキストがわかりやすく、出題される精油の種類も決まっているので対策が取りやすかったです。
香りが好きな人なら1級からでも無理なく学べると思います。
アロマテラピー検定の香り試験廃止
第52回アロマテラピー検定から、香り試験は廃止になりました。
その理由は、香り資材の事前送付による、不正行為の防止が目的とのこと。
実際その試験を受けた感想は、難易度は変わらなかったです。
私は1級のみ受けましたが、代わりの問題はほかの問題と同様に、科名や植物の名前を答えるようなもの追加されていました。
むしろ、香りの試験がない方がスムーズに問題を解くことができるかもしれません。
アロマテラピー検定を受けるメリット
アロマテラピー検定は、単なる資格取得ではなく、香りをもっと楽しむためのきっかけになります。
実際に私も受けてみて、「精油を何滴使えばいいか」「どのシーンで使うとよいか」
など使い方がわかるようになったことで、以前より楽しく香りを使えていると実感できています。
ここでは、アロマテラピー検定を受けるメリットを5つにまとめてご紹介します。
精油の使い方と選び方がよくわかる
香りを「なんとなく」で選ぶのではなく、目的やシーンに合わせて選べるようになります。
たとえば、夜のリラックスにはラベンダー、気分を明るくしたい朝にはオレンジ…など、香りを活用できる感覚が身につきます。
香りの安全な使い方が学べる
精油は自然由来とはいえ、使い方を誤ると体に負担になることも。
この検定では、濃度・保存方法など、薬剤師の立場からも大事だと思うポイントがしっかりカバーされています。
「安心して使えるようになる」のは大きなメリットです。
香りが暮らしの中に根づく
勉強することで、香りを「たまに使う」から「生活の中に取り入れる習慣」に変えられます。
アロマスプレーを作ったり、お風呂に数滴たらしたり、自分なりの“香り習慣”ができるようになります。
アロマショップや精油売り場で迷わなくなる
「どれを選べばいいのか…」と戸惑っていた売り場でも、ラベルの見方や抽出部位の意味がわかるようになります。
それだけでもとても楽しいですし、知識があることで少しだけ愉悦に浸れます(笑)
上位資格・キャリアへの入り口になる
アロマテラピー検定1級を取得すれば、アロマアドバイザーなどの上位資格に進むことも可能です。
美容・医療・介護などの現場で「香りの知識」を活かしたいと考えている方には、最初の一歩としてとても価値のある資格です。
独学で合格できる?【勉強法とおすすめ教材】
アロマテラピー検定は、独学でも十分合格できます。
私自身、忙しい中でのすき間時間を活用しながら、公式テキストと精油セットだけで1級に合格しました。
2025年5月11日(第52回検定)からは「香りテスト」が廃止され、精油セットの購入は必須ではなくなりました。
しかし、実際に香りを確認しながら勉強をすると、
など大きなメリットがあるため、精油セットを同時に購入することをおすすめしています。
また、テキストは最新の2020年6月改訂版を使用してください。古いものは香りの出題変更や内容のズレがあるため注意が必要です。
薬剤師が伝えたい「香りの安全な使い方」
精油(エッセンシャルオイル)は「自然の恵み」ではありますが、正しい知識と使い方があってこそ、その力を活かせるものです。
私は薬剤師として、安全性に関する知識の大切さを改めて感じました。
薬剤師でも、精油の安全性について詳しく知っている人は本当に少ないと思います。
アロマテラピー検定でも基本的なルールや注意点は学べますが、ここではとくに初心者の方に知っておいてほしいポイントを3つにまとめてご紹介します。
精油は“濃縮された成分”。原液使用は基本NG
精油は植物の香り成分をギュッと凝縮したもの。1滴でも非常に濃度が高いため、肌につける・飲むなどの行為はNGです。
必ずディフューザーやお湯、キャリアオイルなどで希釈・拡散して使いましょう。
妊娠中・持病がある場合は注意が必要
一部の精油には、ホルモン系や血圧・神経系に作用する可能性があるものも。
妊娠中、授乳中、または持病がある方は、使用前に必ず専門家に相談してください。
ペット・乳幼児がいる環境では使い方に配慮を
香りに敏感なペット(特に猫・犬)や、免疫が未熟な乳児がいる空間では、使用する精油・濃度・時間帯に十分な配慮が必要です。
換気をしっかり行い、「使用後すぐの部屋に動物や赤ちゃんを入れない」などの工夫をしましょう。
香りは、使い方ひとつで癒しにも負担にもなるもの。
正しく扱って、生活に香りの彩りを加えましょう。
アロマテラピー検定の試験情報まとめ
 画像引用:(公式)日本アロマ環境協会公式サイト
画像引用:(公式)日本アロマ環境協会公式サイト「ちょっと受けてみたいかも」と思った方へ。
ここではアロマテラピー検定の基本的な試験情報を、サクッとまとめてご紹介。
忙しい方でもチャレンジしやすいよう、オンライン・在宅での受験形式になっているのがポイントです。
アロマテラピー検定の試験概要(2025年5月時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主催 | 公益社団法人 日本アロマ環境協会(AEAJ) |
| 試験日 | 年2回(5月・11月) |
| 受験形式 | オンライン受験(自宅のパソコン・スマホから) 選択式 |
| 出題数 | 2級:55問 1級:70問 |
| 試験時間 | 2級:30分 1級:35分 |
| 合格基準 | 正答率80% |
| 受験料 | 1級:6,600円(税込)/2級:6,600円(税込) 併願13,200円(税込み) |
| 合格発表 | 試験後すぐに結果が表示 |
🔗 試験申し込みページ(2025年5月時点)
<次回のご案内>
第53回アロマテラピー検定
実施日:2025年11月9日(日)予定
受付期間:2025年8月21日(木)~10月2日(木)
こんな人におすすめ!検定に向いている人の特徴
アロマテラピー検定は、香りが好きな方だけでなく、日常に“香りの知識”を取り入れたい方に広くおすすめできる資格です。
たとえば、こんな方にぴったりです👇
香りの知識は、“心地よい暮らし”をつくるためのひとつの選択肢。
「これなら自分にもできそう」と感じたら、ぜひ気軽に始めてみてください🌿
まとめ|香りを学ぶことは、自分を整えること
私自身、この資格を通して「ただ好きだった香り」が、暮らしや気持ちを整える大切なツールになりました。
検定に合格することももちろん大切ですが、
一番の収穫は、香りとの向き合い方が変わったことだったように思います。
「いつかやろう」と思っていたことを、今日ここから少しずつ始めてみませんか?
わからないことや、もっと知りたいことがあれば、
このブログでも引き続き情報を発信していきますので、ぜひまた気軽に遊びに来てくださいね。
🔗アロマテラピー検定に出てくる精油を見てみたいかたはこちらを参考にどうぞ👇
▶アロマテラピー検定に出てくる精油
🔗検定は受けなくていいけど、精油は使ってみたいかたはこちらを参考にどうぞ👇
▶【初心者向け】初めての精油(アロマオイル)の選び方&おすすめ5選
▶【初心者向け】アロマを始めるときに必要なアイテム5選+α|実際に買ったものから厳選!
▶【初心者向け】アロマオイルの簡単な使い方4選|ティッシュ1枚から始められる